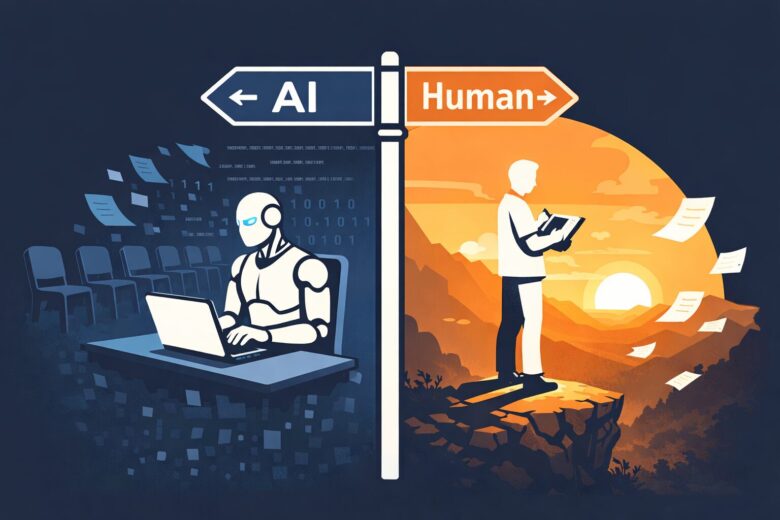生成AIのおかげで、文章は「整える」だけなら簡単になった。
なのに、整えば整うほど——なぜか“薄く”見える文章が増えた気がする。
それは、文章が下手だからじゃない。むしろ逆だ。
上手いのに、誰の声かわからない。
読後に「書いた人」が立ち上がらない。——その瞬間、読む側は少し冷める。
この記事の結論はこうだ。
AIっぽく見えてしまう原因は、品質の低さではなく「代替可能性」にある。
読者が見ているのは「AIか人か」ではなく、
その文章に“誰が、何を捨てて、どこで言い切ったか”という決定の痕跡があるかどうかだ。
この記事では、その痕跡を立ち位置(居場所)と呼ぶ。
立ち位置とは、責任の所在——「私はこれを見て、こう決めた」と言える場所のこと。
そしてAIと自分の文章を共存させる対策も、難しくない。やることは3つだけ。
- 決める:立場を先に固定する
- 切る:捨てた論点を明示する
- 接地する:時間・場所・身体感覚など“一回性”を刺す
……と言っても、抽象のままだとわかりにくい。
だから最初に、10秒のゲームをする。
まずゲーム:AとB、どっちがAIっぽい?
直感で選んでほしい。AとB、どっちが“AIっぽい”?
A
AI時代には文章生成が一般化し、整った文章は短時間で作成可能になりました。
したがって、文章の価値は「正確性」や「網羅性」だけでは測れなくなっています。
読み手は「体験」や「判断」といった固有性を求める傾向があり、
執筆者はそれらを意識的に文章へ組み込むことが重要です。
B
下書きが、一気に完成に近づいた。
論点は漏れない。言い回しもきれい。反論まで先回りして並んでいる。
助かった——と思った、その直後にぞわっとした。
僕モドキが、僕以上のスピードで、僕以上の正確さで議論を繰り広げている。
原稿が整えば整うほど、僕は「作者」から「観客」になっていく気がした。
多くの人はBの方を「人間が書いたもの」と思うだろう。
理由は単純で、Bには立ち位置がある。書いた人がそこに立っている感じがする。
Aは正しい。きれい。
でもAは、誰が書いても成立する匂いがする。
この記事は、この匂いの正体と、立ち位置を取り戻す方法の話だ。
出発点:怖かったのは「速さ」じゃない。「補充可能さ」だった
僕はAIと壁打ちしながら記事の方向性を決めている。
ところが、緻密な文章化(整った原稿)までAIが担いはじめた瞬間、二つの感情が同時に立ち上がった。
- 自分の力以上のものが出てしまう怖さ
- AIが書いたと分かると陳腐に見える違和感
一見すると別の問題に見える。けれど、根は同じだと思う。
まず「自分以上の力が出てしまう」という怖さは、単に“上手い文章が出る”という意味じゃない。
自分が迷い、捨て、言い切ったという手触りより先に、完成品が出てくる。
その瞬間、文章の出来が良いほど、僕は「作者」から一歩引かされる。
成果は出ているのに、責任の場所が自分の側に残らない——その感覚が怖い。
そして「陳腐に見える」という違和感も、結局は同じ地点に触れている。
怖いのは“速さ”そのものではない。
速さによって言葉がいくらでも補充可能になり、結果として「いま、この人が言った」という来歴が薄れていく。
その不可視性が、読者の目には“薄さ”として映る。
要するに、恐怖も違和感も「来歴が薄れる」一点に収束する。
用語を固定する:「薄い」「陳腐化」「量産感」
最初はこう説明しがちだ。
AIが書いたと分かる → 価値が落ちる
でも、これは雑だ。落ちているのはラベルというより、文章から立ち上がる量産感に近い。
ここで言葉を固定しておく。
- 薄い:読後に「誰の声か」が立ち上がらない
- 陳腐化:低品質ではなく、言葉が代替可能に見えて価値が下がる現象
- 量産感:どこにでも置けて、角がなく、誰が言っても成立しそうだという印象
つまり、ここでいう陳腐化は「内容が悪い」ことじゃない。
代替可能性が透けることだ。
読者は無意識に「誰の声か」を判定している
生成AIが一般化して以降、文章を読むとき、読者は無意識に「これは誰の声か」を確かめにいく。少なくとも僕の観測では、この挙動は強まった。
ここでいう「判定」は、AI検知ツールの精度の話ではない。もっと素朴な現象だ。
読者は、たとえばこんな点を見ている。
- どこかで見た言い回しではないか
- 反対意見を恐れて丸めていないか
- 誰が言っても成立する最大公約数ではないか
- 結論に至るまでの選別や迷いが見えるか
ここでの判定は「人間かどうか」ではなく、決定の痕跡があるかどうかを探す読みが潜んでいる。
余談として、アラン・チューリングは1950年に「機械は思考できるか」をめぐって、
テキストだけの対話で見分けがつくか、という“模倣ゲーム”(チューリングテスト)を提案した。
当時は「騙せるほど賢いならすごい」という方向に、技術の前向きさが働いていた。
けれど今は逆だ。
読者は「騙されたい」より先に、「誰の声か」を確かめにいく。ここに、冷えの回路が入り込む。
さて重要なのはここからだ。
読者が冷めるのは「機械が書いたから」ではなく、誰が書いたとしても成立してしまうから
——つまり、代替可能性が透けるからだ。
“薄さ”の正体は下手さじゃない。無重力だ
薄い文章は、下手な文章とは限らない。むしろ「上手い」側にいることが多い。
ここでいう薄さは、情報量の少なさではない。
書き手の選択(何を捨てたか)と責任(どこで言い切ったか)が見えない。
その状態を、僕は「無重力」と呼びたい。
薄さの正体を一行で言うとこうなる。
読者が「誰でも書ける」と感じた瞬間、文章は無重力になる。
無重力な文章には、よくある特徴がある。
- 何も捨てていない(全部入っているから輪郭がない)
- どこでも成立する(時間・場所・身体感覚がない)
- 結論が弱い(言い切りがない)
- 無敵っぽい(反論しても削れない)
これらは「丁寧さ」と紙一重だ。だから怖い。丁寧にするほど薄くなることがある。
もちろん、マニュアルやFAQのように「丁寧=価値」の文章もある。
問題は、考えや経験を語りたい文章まで同じ質感になってしまうときだ。
作品の価値:誰が何を捨て、どこで賭けたか
ここで焦点を一本にする。僕が扱いたいのは「関係の価値」ではなく、作品の価値だ。
作品価値とは、ざっくりこういうことだと思う。
- 来歴(決定の痕跡):その結論に至るまでの道筋が見える
- 選別:何を捨てたかが見える
- 賭け:どこで言い切ったかが見える
整っているだけでは作品にならない。
作品は「選別の痕跡」で立ち上がる。
アウラ=「取り替えの効かなさ」——薄さを説明する比喩
ここで言う「アウラ」は、ヴァルター・ベンヤミンが『複製技術時代の芸術作品』で論じた概念を、
比喩として借りるものだ。
アウラは「神秘的な雰囲気、オーラ」ではない。
ベンヤミンの問題意識を、要約するとこうなる。
昔の芸術作品は、寺や劇場や特定の場に「そこでしか会えない」形で存在していた。
距離や儀礼や時間が、作品を“ここ・いま”に縛っていた。
ところが写真や映画などの複製技術が進むと、作品はどこへでも運ばれ、同じ姿で反復される。
すると作品にまとわりついていた「その場に立ち会っている感じ」や「ここでしか起きない必然性」が薄れていく
——この、唯一性/現前感のまとまりを、彼はアウラとして語った。
複製が進むほど、その「そこでしか起きない必然性」は薄れやすい。
そこでこの記事では、この核だけを使う。
アウラ=“ここ・いま”の必然性(取り替えの効かなさ)
生成が容易になるほど、言葉は「どこにでもある」ものになる。
「どこにでもある」言葉は、「誰のものでもない」ものに見える。
そのとき読者は内容より先に、代替可能性(量産感)を嗅ぎ取る。
この構造を、AI文章に当てはめるとこう読める。
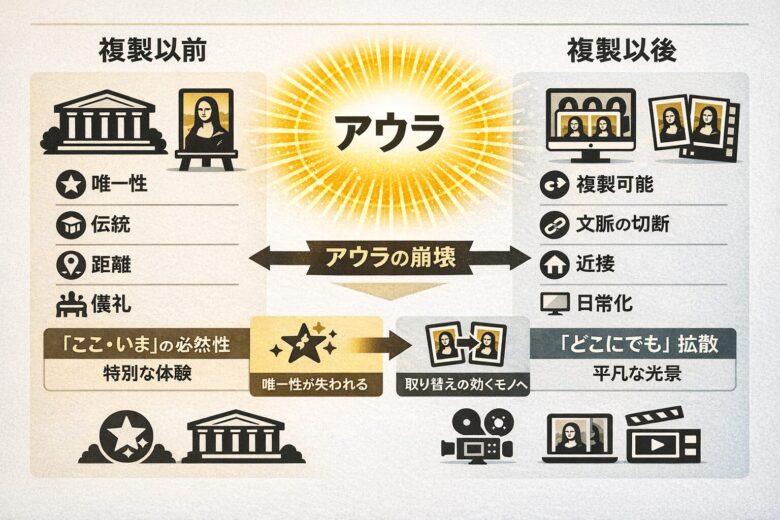
「アウラ ⇄ AI文章」
- アウラの核:唯一の現前(ここにしかない)
↔ AI時代の核:その人の体験と判断(この人にしかない)
※唯一性は「物理的に一つ」ではなく、「この場・この人の必然性が立ち上がる」という意味で使う。 - 複製で起きること:どこでも同じものが現れる
↔ 生成で起きること:誰でも同じ“それっぽさ”が出る
→ 生成が増えるほど、表現は「代替可能」に見えやすくなる(=誰が書いても成立しそう、という知覚)。 - 受け手の変化:作品を見る前に「量産可能性」を感じる
↔ 文章を読む前に「AIっぽい匂い」を嗅ぎ取る
→ ここでの匂いは検知の話ではなく、「決定の痕跡が薄そうだ」という予感として働く。
だから僕が戻したいのは“人間らしさ”ではない。
戻したいのは、判断の来歴——何を捨て、どこで言い切ったかの痕跡だ。
立ち位置はどこに宿る?——体験と判断
読者が「これはあなたの文章だ」と感じるとき、見ているのは文法の正しさではない。
もっと単純な二つだと思う。
- 体験:あなたが“そこで”何を見たか
- 判断:それを見て、何を決めたか
AIが得意なのは整形(きれいにすること)だ。
でも体験と判断は、たとえそれっぽく書けたとしても、借り物に見えやすい。
だから主語を取り戻す最短ルールはこれになる。
体験と判断は自分。整形はAI。
体験は「事件」じゃなくていい。1行で“現場”は戻る
体験というと大げさに聞こえるけれど、必要なのは派手さではない。
- いつ
- どこ
- 身体感覚(手が止まった、息が浅い、胃が重い)
これが入ると文章は一気に“現場”を持つ。
たとえば、こういう一行。
下書きが一気に完成に近づいた瞬間、達成感より先にぞわっとした。
この一行がその後の判断を支えるとき、読む側は「あなたがそこにいた」ことを信じやすくなる。
書き手が立ち上がる。
判断は「偉い意見」じゃない。線引きでいい
体験だけだと日記で終わる。文章を作品にするのは判断だ。
判断は、大きな思想じゃなくていい。線引きでいい。
- この記事で言い切るのはこれ
- それ以外は扱わない
- ここは譲らない
たとえば、この判断で十分だ。
僕は、整った文章を作りたいんじゃない。僕の立ち位置を守りたい。
これが判断だ。ここで書き手が立つ。
今日から使えるテンプレ
持って帰れる形にする。
① 体験(2行)
- いつ/どこで:____
- 何が起きて/身体感覚:____
② 判断(1行)
- だから僕は:____(結論・線引き)
これを記事のどこかに入れる。たったそれだけで、薄くなりにくい。
AIへの頼み方を変える ——平均化ではなく「主語の検査」
AIを“平均化マシン”として使うと薄くなる。
“主語を検査する装置”として使うと強くなる。
使える指示はこれだ。
- 「ここで僕が消えてる箇所を指摘して」
- 「この文章の『誰でも言える部分』を削って」
- 「結論を1行に尖らせて。僕が責任を持てる形に」
- 「反論を出して。その上で残る一文を作って」
- 「僕が捨てるべき論点を3つ挙げて。捨てた理由も書いて」
一般論が悪いわけじゃない。
でも一般論“だけ”だと、書き手が見えにくい。
だからAIには「網羅」よりも「削る」「尖らせる」「選別を可視化する」をやらせたほうがいい。
眼鏡みたいに、AIは視界を澄ませる道具だ。
ただし、どこを見るかを決めるのは僕だ。
結論:判定されても価値が落ちない痕跡を設計する
AI時代の文章は「AIかどうか」より、量産可能な声かどうかで裁かれる。
だから狙うべきは“脱色”ではない。量産できない決定の痕跡を文章の中に残すことだ。
実装は、これで足りる。
- 決める:立場を先に固定する(逃げ道を減らす)
- 切る:捨てた論点を明示する(総花=薄さの罠を避ける)
- 接地する:時間・場所・身体・気まずさなど、自分の“一回性”を1つ刺す
僕モドキは速い。正確だ。整形が上手い。
だから使う。使わない理由はない。
でも線は引く。
体験と判断は自分。整形はAI。
AIに文章を整えさせてもいい。
けれど「その夜に何が起きて、僕がどう決めたか」だけは渡さない。
そこが残っている限り、完成した文章の中に、まだ僕の立ち位置がある。